娘が気に入っているオモチャのひとつがゴム製のクモ。
100円ショップかどこかで買ったのですが、ムダにリアリズムを追求していて、気持ち悪いのです。
長男が保育園に持って行って、保父さんが「ウヒャー!」となった代物です。
それを娘は好んでベロベロ舐めてます。数あるオモチャの中からこれをチョイスしてはベロベロ舐めてます。
初めてこの光景を見たときは、私も「ウヒャー!」となりました。
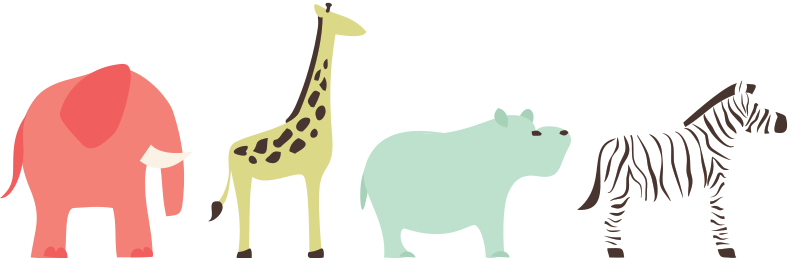
 |
バースト・ゾーン―爆裂地区 (ハヤカワ文庫JA) 吉村 萬壱 早川書房 2008-04 by G-Tools |
吉村萬壱はスッと頭に入ってくる文章で、グチャグチャなものを描く作家さんです。
読み終わったあとは心に傷を残してくれること請け合いです。
で、本書「バーストゾーン」です。
舞台となる国(日本っぽい)の民衆たちは、「テロリン」という過激派によって緊迫した生活を強いられています。
一方、「テロリン」の本拠地とされる大陸に派遣される志願兵たち。
大陸に向かう船で繰り広げられる狂宴は一体なんのために行なわれているのか?
「テロリン」の正体とは一体? 「テロリン」を殲滅する究極兵器「神充」とは?
と言ったストーリーです。
基本的に吉村萬壱的なエログロな場面の連続ですが、サディスティックな願望を満たすために書かれたもの、と解釈するにはもったいない作品です。
暴力描写は「人間を人間としているものとは」という問いに対しての答えを探すための、道具立てなのだと石之介は思っています。
死や暴力によって、登場する人たちはどんどん人間性を否定されます。
でも最終的には精神的な否定を身に着けたもののみが生き残る、という物語になっています。
(登場人物は人間的な行動をしようもんなら殺されちゃいます。)
☆☆☆☆以下、ネタバレあります。☆☆☆☆
実は「テロリン」なんてものは存在しません。
大陸に存在するのは「神充」という謎の生き物だけなのです。それを国民は知らされていません。
主人公たちがいる国以外の国は「神充」によって滅ぼされています。
「神充」は人間を嫌います。人間が頭の中に持つ「意味性」を嫌います。だから人間の脳みそを吸って排泄して、滅ぼすのです。
で、なぜこの国だけが保たれているのかというと、『志願兵による犠牲』と『「テロリン」に対する憎悪/それによって発生する愛国心という強烈な意味性』によって神充の侵略を防いでいるからなんですね。政府によって。
強烈な意味性は「神充」にとって毒なのです。
という仕掛けがこの物語にはあります。SF的ですね。
神充という存在は人間によって決して倒すことのできない天敵として描かれています。
そういわれると、人間にとって天敵と呼べる生物がいませんね。
だから、もし天敵が現れたら、といったことを考えた場合、この国が取っている政策はとても非人間的なものでありますが、生存戦略としては優れているのです。(他の国は失敗しているから)
で、「神充」だけでなく、著者も文章中で言葉の意味を殺したりしています。
例えば登場人物が絶望の中、愛する人の名をつぶやくが、聞いていた人間には別の意味と解釈され、さらに殺されるというシーンが、石之介が覚えているだけでも2つあります。
1.「智代」 → 友よ との呼びかけと勘違いして、嫌悪する(殺す)
2.「さわら(ぎ)」 → さわらないでと言われたと勘違いして、激怒する (殺す)
これは、「自分にとっての言葉は他人にとっての言葉と同じとは限らない」という言葉によるコミュニケーションの限界を、お得意の殺戮/陵辱によって表現しているだと思います。
あと、不思議なことがひとつありました。
第一章ではあれほどディストピアに見えていた祖国が、大陸(第二章)を経て、大陸から帰ってくると(第三章)、ものすごーく安心感のあるところに感じるんですね。
※でも、結局一番残酷なシーンとして心にのこったのは、上記の「友よ…」の部分だったんですけどね。嫌悪感というか。
脳みそ吸われるシーンより、人が人を殺すシーンの方が、描くのうまいんだよ、この人は。サイテーです(作家としては最高です。)
お気に入り度=☆☆☆☆☆
クチュクチュバーンと張るくらい好きかもしれない。
暴力表現が平気な(さらに影響されない)人は是非。
色々思うところあって、ちょっと前から英語を勉強しているのですが、教科書的なもので勉強していてもどうもテンションが上がりません。驚く程上がりません。
そりゃそうです。「ボブは論理的というよりも直感的だ」みたいな文章ばっかりで、ションボリです。
ということで、やる気を失わない勉強法として「興味があるコトの英語のwebサイトを読む!」にしました。
で、つい読みふけってしまうサイトってなんだろう、って考えたところ、以前「wikipedia」で興味のある項目を次々読んで行くってのにけっこうハマったので、これを英語でやったらどうだろう、と。
英語版「wikipedia」
例えば、『Dragon Quest』とか調べちゃいますと、「ドラクエ1」は英語版だと「「Dragon Warrior」って言うんだ」とか「ローラ姫の名前も英語版だとグウェリンとかいうあんまり萌えっとしなそうな名前」なんだ、とか楽しめちゃいます。
で、発音がわからない単語なんか出て来たら、MACの読み上げ機能を使って読ませちゃいます。
MAC使っててよかった。
意外と楽しめてます。オススメです。
 |
キマイラの新しい城 (講談社文庫) 殊能 将之 講談社 2007-08-11 by G-Tools |
『ハサミ男』を読んだら、殊能将之のいたずらっ子的な作品がもっと読みたいとか思ったので、本書『キマイラの新しい城』を手に取ってみました。
ストーリーは中世の騎士「エドガー・ランペール」が現代日本に蘇って(人に乗り移って)、自分の死の真相を知ろうとする、というもの。
エドガー・ランペール視点と三人称視点を交互に追いながら、物語は進んで行きます。
物語を追って行くと、さらに現代でも不穏な動き。殺人事件が起きてしまいます。
さらに、エドガー・ランペールに乗り移られた江里という男は、実は乗り移られていないんじゃないのか? 演技または思い込みなのではないか?という疑問も提示されていきます。
つまり、エドガー・ランペールじゃない頃の江里がどのような人物であったのか、という点も謎のひとつとなります。
まあ、そういったミステリ部分を追うのも楽しいんですが、この作品で読むべきはエドガー・ランペール視点の現代の風景。
地名なんかは東京→トキオーン、六本木ヒルズ→ロポンギルズと中世風に。人名も石動→イスルギーなんて感じで。
バイクや車を、奇妙な動物と思ったりするのは、ありがちといえばありがちなシーンですが、エドガーの大仰なものいいで表されるので、なんだかかわいいです。
週刊少年ジャンプであろう書物を見つけたときは「人が素手で格闘したり、剣を交えている絵が多い。字が読めぬ者のための武芸指南書であろうか」とか言っちゃうんです。
この読み心地は、森見登美彦作品に通じるものがあるかもです。
三人称視点はマジメかというと、正直言って悪ふざけしてると思うんですよ。(ホメてます)
地の文で石動のことを、「名探偵の石動戯作は」とか言っちゃってるんです。何回も。”名”は書かないですよね
普通。
しかも名探偵って何回も言ってたのに、結局石動は解決しないんですよ、事件を。別の人が解決しますけども。
ラストは、ちょっと切ないです。
切なく描こうとしているわけではなさそうですが、エドガー・ランペールのことを好きになってしまったので、「ああ、そうなのか」という感じで。
お気に入り度=☆☆☆☆
殊能将之の別の作品も読みたくなって来ました!
 |
サウンドトラック 古川 日出男 集英社 2003-09by G-Tools |
古川日出男の文章をどうしても読みたくなってしまうことがあります。
そんなわけで、古川節をたっぷり味わえそうなこの作品をチョイス。
【内容情報】(「BOOK」データベースより)
![]()
2009年、ヒートアイランド化した東京。神楽坂にはアザーンが流れ、西荻窪ではガイコクジン排斥の嵐が吹き荒れていた。破壊者として、解放者として、あるいは救済者として、生き残る少年/少女たち。これは真実か夢か。『アラビアの夜の種族』の著者が放つ、衝撃の21世紀型青春小説。
大変書評が書きづらい作品です。
物語というのは性質上、ばらまかれた状況を収束するものですが、この作品は点がいっこうに線になっていかないのです。
でも、古川日出男の文章にしびれちゃってるんで、最後まで読み切らされました。
まず冒頭。
無人島に放り出された幼いトウタとヒツジコ。
幼い弱々しい生命という存在に不安を覚えてしまうけども、生き延びる二人にホッと安心。
ルーツと言葉をなくしている(つまり社会的に人間でない)二人がどんな風に物語を紡いでいくのかと期待してしまいます。
でも、東京編に入ってからは、二人がどうなるのか、どうしたいのかが全然わかりません。
(無目的であることを描いているのかもしれませんし、不可解でありながらも面白いことをしていたりするのですが)
最終的にもトウタとヒツジコの物語は収束していきませんでした。
あれほど運命的な冒頭だったのに。
と、まあ批判的なことを書いてしまいましたが、それでもこの作品は面白かったです。
なにしろ第三の主人公とも言えるレニが良いです。
正確にはレニのまわりにいるキャラクターがすごく好き。
人語を解するカラス・クロイ。
カラスなのに、映画を見るし、人を助けるし、家族愛を感じるし、そして最後には神になる。
あと、個人的に本作品で一番好きな、レニの映画の師匠・居貫。
カラスに対して、真剣にサイレント映画を見せる巨体の男。
で、性別を持たない存在・レニ。
少女にも少年にもなれる存在。
まあ、このレニとクロイと居貫が、侵入した体育館でサイレント映画を見るシーンなんか想像するだけで、わくわくしちゃいます。
レニ編だけで良いから、だれかオシャレ映画撮ってくれないかな。絶対見に行きます。
他にも魅力的なキャラクターがたくさんいます。
トウタ編に出てくる神殿の女神・ピアス。
ヒツジコ編に出てくる「免疫体」の3人。
自分の妄執のためにヒツジコのお母さんになるうずめ。
など、それぞれのキャラクターごとにひとつの作品が描けるんじゃないかと思うくらい、特徴的なキャラクターたち。
魅力的な文体とキャラクターさえあれば、「ストーリーを追う」必要はないのかな、とか考えさせられました。
ところで、東京+熱帯(+破壊)と言えば、池上 永一 『シャングリラ』を思い出してしまいましたね。
あれも破綻している部分はあるのにパワーを保持している面白い作品でした。
お気に入り度=☆☆☆☆
機会があれば、もう一回読みます。
時間とエネルギーのある時に。
その時は五つ星をつけてしまうような気がします。
稲毛浅間神社へ昨年のお守りや熊手を納めに行って来ました。
昨年の今頃は、この稲毛浅間神社のすぐそばのマンションに住んでいたので、懐かしい気もします。
靴を初めて履いた娘は、神社で歩き回りです。
例年は、破魔矢や熊手を買って行くのですが、今年は経済的にアレなので、交通安全のステッカーと長男用に小さいおまけ付きのおみくじだけ。
おみくじのおまけは金魚が出て来ました。金運が良くなるって。
ナイス長男。
あと、神社に来るとついやってしまうのが、『絵馬を読む』です。
色んなひとが書いた色んな願い事を読むと、なんだか楽しい気分になっちゃいますね。
勝手に読んでスイマセンとも思いますけども。
その後は近くの公園で子供たちを遊ばせて、ご帰宅です。
寒い日が続きますが、晴れた日は近くの公園や海岸で外ゴハンということにしています。
今日は習志野緑地(香澄公園)。
ウチのマンションの裏から習志野方面に延びている細長ーい公園です。
キロ単位で細長いので、適当に歩いて、日当りのよさそうなところでレジャーシートを広げちゃいます。
そこで、お菓子とかおにぎりとかを広げて、食べましたんですが、なんだかいつもよりウマく感じる!
「外で食べるから、おいしく感じるのかな」なんて粋なコトを申してみましたところ
「今日のシャケはいいシャケなんだよ」という嫁の答え。
なんでも会社でグルメな人から良いシャケを仕入れて来たんですって。まあ。
石之介は味オンチであることに多大なる自信を持っていたのですが、残念ながら『良いシャケはおいしい』ということが分かってしまいました。
シャケおにぎり in the sky。
休日のパパには「子供を疲れさせる」という重大な使命があります。
疲れさせて、夜寝かしつけるママを少しでも楽にするためです。
でも、真冬は寒いので、外で遊びすぎてカゼでもひかせたら、逆にママに負担を掛けてしまいます。
で、思いついたのが、温水プールです。(ヨメが)
暖かいころにはよく行ってたのですが、寒い中にプールというのはなかなか思いつきませんでした。
早速行ってみました。
夏には空いている天井のドームはもちろん閉まっています。
温水プールはほどよく温かく、気持ちよく水遊びが出来ます。
しかも、ここは全体的にガラス張りなので、冬なのに日差しが気持ちいいです。
水から出た後はもちろんアイスとラーメン。
なんで、こんなにも食べたくなるんでしょうね。(他のご家族もみんな食べてました)
あけましておめでとうございます。
やっぱり年明けなので、「今年の抱負」的なものを表明します。
今年の抱負は『目の前のことを、マジメにやる。』です。
じゃ、去年は不マジメにやっていたのかというと、
そういうことではなくて(そうかもしれないけど)、
そんなに気張らなくても大抵のことはやれてしまう年齢になってきちゃったせいか
日々の生活を『こなす』感覚でやっちゃってるんですね。
(忙しいは忙しいんですが)
もうちょい若い頃は、いちいち過剰なエネルギーを放出しては
後で凹んだり反省したりしていた訳ですが、
そういう情熱がなくなっちゃったな、と。
年末年始に掛けてふと考えてみたら、
そんな感覚で生きるのはまだ若すぎるぞ、と反省したワケでございます。
ということで、今年は少年の頃に持っていたワクワク感を取り戻そう、と。
で、今年の抱負の『目の前のことを、マジメにやる。』は
『目の前にないことはやらないぞ、コノヤロウ。その代わり、目に入ったモノはものすごくやるぜ』という決意表明であり
今年のオレは視野が狭いぜ。バランスなんかも取らないぜ。というたいへん不マジメな宣言でもあります。
すいません。
初詣は、実家近くの拝島大師。下の子と一緒に新年のご祈願。