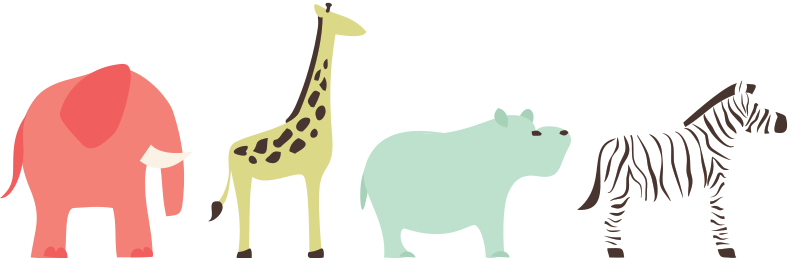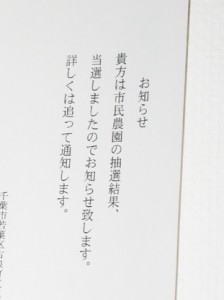生活に少し疲れている時は、「物語を追う必要がない文章」を読みたくなることがあります。
感情移入するパワーがないので、物語を楽しめないからだと思います。
そんな時は先人のことばを頂戴するに限ります。
ということで『バカの壁 (新潮新書) 』がバカ売れした養老孟司先生の本を読むことにしました。
』がバカ売れした養老孟司先生の本を読むことにしました。
なるほど!と思った点はいくつかあったのですが、特に印象深いのは2点。
1・日本の「物づくり」指向について
「日本人はやっぱり物づくりだ」というような論調を無批判に受け入れてた石之介ですが、それに対して、「なぜ」「いつから」そうなったかということに関して考えたことがありませんでした。
それに対し、養老孟司先生はこう説きます。
どうして物づくりか。問題はその動機である。NHKの「プロジェクトX」という番組も、日本人の物づくりの熱心さをいいたいのだと思う。なぜそうなったのか。答えは戦争にある。あるいは敗戦、終戦にある。
ご存知のように戦後は価値観がいわば逆転した。私の世代なら「だまされた」と感じた人が多いはずである。戦争にはかならず勝つ。そう教えられて育ってきたからである。社会的価値観のそうした逆転現象に出会うと、「変わらない」ものを求める気落ちがどうしても生じる。
〜略〜
文科系的な価値観は信用がおけなくなった。理科系つまり科学技術なら間違いあるまい。そういうことである。
なるほど。日本人は敗戦後、気持ちのヨリドコロとして、「物」=「確実さ」を選択したわけなんですね。
で、敗戦経験者はその経験を以て、次世代を教育する。確実であれ、と。
そうして生まれたのが、超保守的な世代、団塊の世代なのかな。どうなんだろ。
石之介はちょうどロスジェネ世代ど真ん中なので、「私の世代なら「だまされた」と感じた人が多いはずである。」という記述にも目をひかれてしまいます。社会なんて信用できない、なんて状況は常にあることなんだな、ということなんですね。先生。
ボクら世代の人間は社会に対してつい被害者ヅラしてしまいがちな気がする。ちょい反省です。
あと、戦争への言及関連で言うと、「拝啓 小泉首相様」では少し泣いてしまいました。
2.「自分探し」と「仕事」について
「自分探し」という言葉について回る胡散臭さについては、自分としても気になるところではありましたが、養老先生がヒントをくれました。
「本当の自分」があったって、べつにかまわないのだが、それを「自分の意識が把握できる」と思ってるのが、とんでもない間違いなのである。
〜略〜
「本当の自分」という錯覚が、職業選択に影響していることは、若者たちが「自分に合った仕事」を探しているという調査結果からもわかる
「自分探し」に感じる違和感は、自分とかいうものがある/なしの話じゃなくて、あったとしても、そもそも認識できるか、という話なんですね!
認識できないものを一生懸命探しても見つかるはずありませんよね。
さらには見えないものに合った「仕事」を探すことなんかそもそも無理なんだ、と。
おーっと、明日から会社に行くことが少しラクになりましたよ。ありがとうございます。養老先生。
っと、そこでまた新たな疑問が生まれました。
「自分探し」とかって誰が言い出したんですかね? 今後、要調査です。