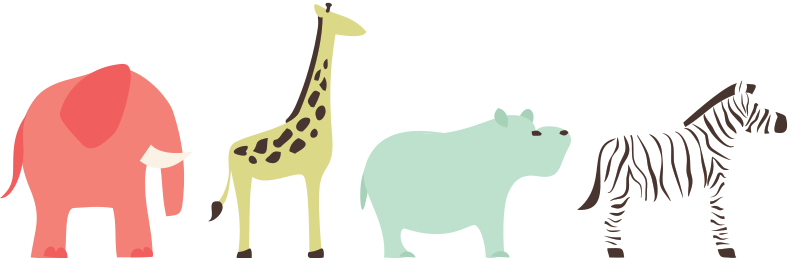|
独白するユニバーサル横メルカトル 平山 夢明 by G-Tools |
平山夢明には、「狂い」の構造 (扶桑社新書 19)を読んでから興味がありました。
平山夢明は社会にうまいこと適合できた狂人のような人、と石之介は認識しています。
正常な人が「狂った世界」を描いた場合には、「正常」の裏としての「狂い」が描かれて、そこにはタブーを犯していることに対する陶酔が盛り込まれちゃったりしがちなのですが、平山夢明の場合は自ら見えている世界を「正常」な人たちに対して翻訳しているかのように描いているように思えます。
作品は面白いですが、近くにいたらすごくコワい人かと思います。
で、本書『独白するユニバーサル横メルカトル』です。
8編の短編からなる本書ですが、まあ馴染みのある世界はひとつもないです。
「C10H14N2(ニコチン)と少年–乞食と老婆」
この作品に関しては乞食側に感情移入してしまったもんだから、切なくて仕方が無かった、といいたいところですが、思わず笑ってしまった何箇所があります。
一つはたろうが乞食に対して、なんでそんなに暮らしをしているかを問うシーンで次々とダメな理由をあげていくところ。特に以下の台詞。
「じゃあ、お酒だ。お酒のみだったのでしょう(アル中だ)」
この作品では()付きの台詞はこの部分だけなのに、大変失礼な決めつけをいきなりしてしまっているんですね。伝わりづらいかもしれませんが、会話の流れで読むと笑えるはず(と石之介は思っています)。
ほかにも乞食に対して失礼なナレーションやおじいさんにいきなりキレるたろうなど、全編通して笑える部分がちりばめられています。(笑えるという読み方は誤読かもしれませんが)
「Ωの聖餐」
食人をするオメガと、その世話をする男の話。
なぜかハードボイルドを感じさせる世界感。結末に関しては予想通り、というか、実は話の中でほのめかされているので、意外性は少ないけど、とらえようによってはハッピーエンドかな?
「無垢の祈り」
実の母にも義父にも同級生にもいじめられている少女が殺人犯に救いを求める話。
いやー、実際に世界がこういう風に見えている子って多い気がするなー。
こういうのはフィクションの中でだけでやって欲しいけど……。
「オペラントの肖像」
ディストピアものっていっていいんでしょうか。
管理社会において芸術がタブーとなっている世界。
この世界観で別の話が読みたいなー。
チャンピオンとかで長期物としてマンガ化してほしいです。
「卵男」
死刑囚@監獄。
これが一番ミステリっぽいかも。
とはいえ、結末がものすごい意外かっていうと、そうでもない。
「すまじき熱帯」
本書でこれが一番あたまおかしいな、って思います。
外国語で書かれた作品を、うまく翻訳できなかったみたいな文章が刺激的です。面白いです。
これをたとえば1500枚くらい続けたら、新しいジャンルになりそう。
「独白するユニバーサル横メルカトル」
地図が独白するところから始まるのですが、あまりの丁寧なものいいに正直笑ってしまいました。
人皮の不気味さも良いです。
ストーリー的にはちょっと物足りない気も。
「怪物のような顔の女と溶けた時計のような頭の男」
いや、すいません。わりとグロテスク描写には強いと自負していましたが、読み切れませんでした。
お気に入り度=☆☆☆☆
グロテスクな作品がほとんどですが、読後感はそんなに悪くないです。
でも『このミス』1位という事実に対しては、疑問。ミステリ性がある作品が多い訳でもないのに。
『このミス』の言う広義のミステリってイコール小説全てってことなのかな。もうジャンルにこだわる時代でもないですよ、ってことかな。