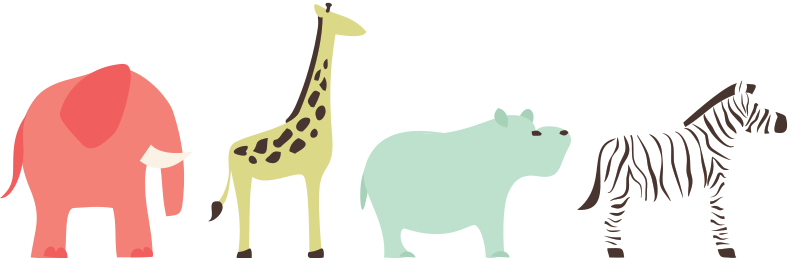|
最後の物たちの国で (白水Uブックス―海外小説の誘惑) Paul Auster 柴田 元幸 白水社 1999-07 by G-Tools |
ポール・オースターの作品は、手に取ってみたくなるタイトルが多いですよね。
いったいどんな作品なんだろうかと思わせるような。
『ティンブクトゥ』や『偶然の音楽 (新潮文庫)
』や。
そんな中で今回は『最後の物たちの国で』を読んでみました。
舞台は名前が示されない、荒涼とした国。
殺人や略奪が日常として行われており、次の瞬間に生きていられるかどうかわからない、という程の殺伐した世界。
そんな場所での、主人公:アンナ・ブルームの暮らしが、手記の形で綴られます。
「自殺するのが怖いので、代わりに自分を殺してくれる」という商売が成り立つほど死んだ方がましだというほど絶望に満ちた世界にいるのに、アンナは他人を救おうと試みたり、幸せな未来を築こうとしてみたりなど、なかなかのタフネスを見せてくれます。
それらの行為は感情を抑えつつ淡々と綴られており、状況に対するあきらめを抱きつつも、それでも一歩でも先に進んでみせようという矜持を感じさせて、グッときました。
こんな世界は現代日本に生きる私たちにとっては、異世界であると思いつつも、実際にこんな絶望感に満ちた時代・国はいくらでもあるようにも感じます。
現実と違うところは、「失われた物は忘却される」という点。
現実では例えば目の前の「えんぴつ」が手元からなくなったからといって、「えんぴつ」という物自体を忘れる訳ではないですよね。「えんぴつ? 何それ?」というような。
人間が他の生き物と違うのは、記憶や記録によって「物が実際になくても」後世に物を残すことが出来る、という点だと思うのですが、この世界では”ある”物しか残っていかないワケですよ。
これは恐ろしいですよ。
未来は近眼的な世界になっていくしかない。
この作品そのものである主人公の手記も「残された物」であるわけですが、この手記が失われたら、主人公も忘却され失われるのかもしれません。
お気に入り度=☆☆☆☆☆
見事なディストピアもの。
同じく死に満ちた、人がグチャグチャと死んでいく吉村萬壱的な世界とは別の絶望感があります。
でも、読後感はなぜかさわやか。
もう一回読もう。